321209 高知県/炭竹 万能へら/バターナイフ

こちらは炭竹-すみたけ-で作られた「万能へら」と「バターナイフ」です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。
それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。
この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

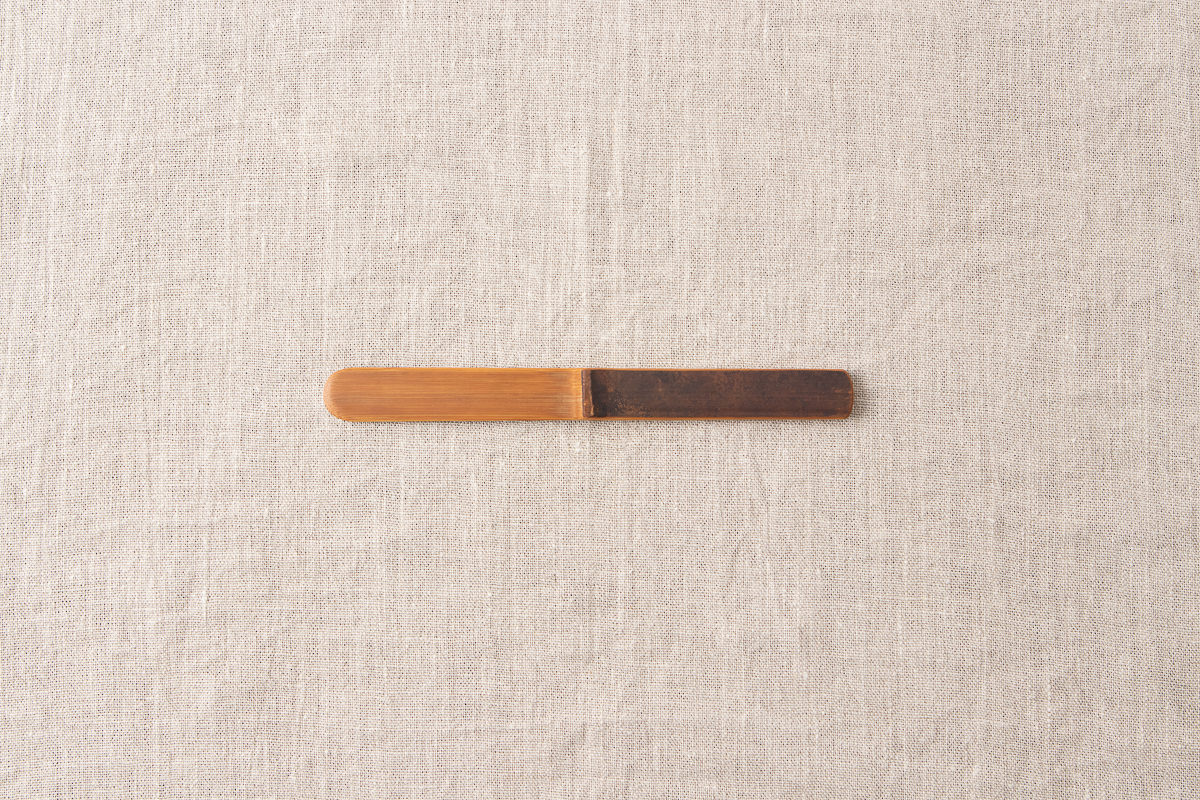
こちらは「万能へら」。アイスキャンディのスティックのようなかたちをしていますが、しっかりとした太さと厚みがあります。 
こちらがへらの先で、塗ったり練ったり和えたりするところです。 
へらの刃先は、1mmもないほどの薄さ。とはいえ、シュッと指を傷つけてしまうような鋭さはなく、やさしい手あたりです。 
へらの先端もなめらかな丸みを持っています。食材を和えたりするときにも、器や鍋を傷つけにくい仕様です。 
ヘラの柄は握りやすいように厚みがしっかりと取られています。炭竹ならではの燻した竹の表情にも味わいあります。 
その名前のとおり、いろいろな場面でお使いいただけます。サラダを和えたり。 
ジャムや餡を塗ったり。ケーキのクリームを塗るとき、餡を練るときにも。 

ほかにも、おひたしを和えたりや納豆をまぜたりと、お料理のいろいろな場面で活躍します。 

こちらはバターナイフです。万能へらにくらべるとシャープなデザインです。 
ナイフの刃部分です。写真の刃上側は平らに、下側はバターが切りやすいようナイフ状になっています。 
こちらも薄いつくりですが、シュッと指を傷つけてしまうような鋭さはありません。やさしい手当たりです。 
ナイフの柄は握りやすい厚みになっています。燻された竹の風合いが感じられます。 
裏面の様子です。 

刃のところでバターを切り、平らに塗り広げたいときは、上の部分の平らなところを使います。 
左利きの方もおなじような使い方ができます。

いい道具を使って料理をしたり食事をしたりしていると、
なんだかとてもいい時間を過ごしているような気分になります。
そんな日々の小さな幸せを作り出してくれそうな、2つの道具です。
どちらかお好みのタイプをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__
高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、
もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、
その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする
「炭焼き」を本業とされていました。
炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを
つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに
炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。
日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。
下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに
自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって
生活の道具としてのカトラリーを作られています。
下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、
どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく
手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。
長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、
もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに
より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、
小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。

こちらは炭竹-すみたけ-で作られた「万能へら」と「バターナイフ」です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。
それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。
この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

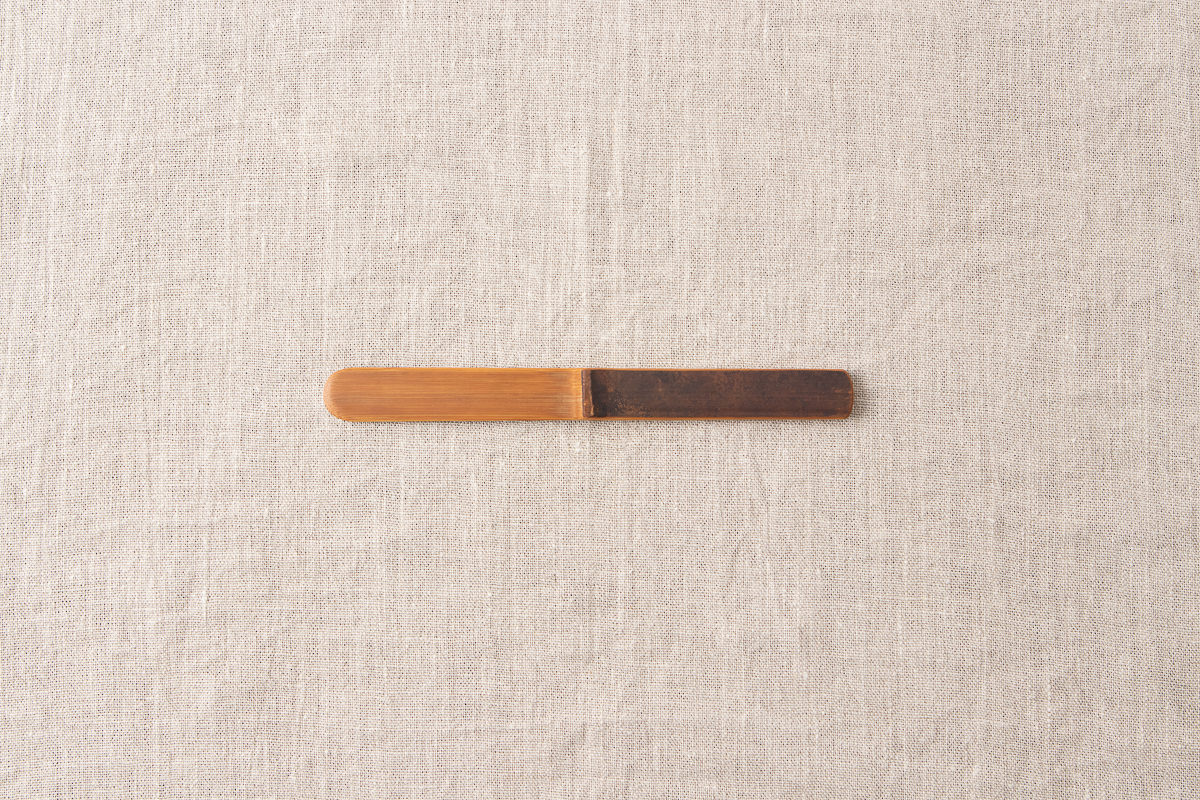


















いい道具を使って料理をしたり食事をしたりしていると、
なんだかとてもいい時間を過ごしているような気分になります。
そんな日々の小さな幸せを作り出してくれそうな、2つの道具です。
どちらかお好みのタイプをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__
高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、
もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、
その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする
「炭焼き」を本業とされていました。
炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを
つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに
炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。
日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。
下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに
自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって
生活の道具としてのカトラリーを作られています。
下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、
どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく
手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。
長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、
もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに
より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、
小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。

こちらは炭竹-すみたけ-で作られた「万能へら」と「バターナイフ」です。

竹のなかでも勢いがありしっかりした太さのある「孟宗竹-もうそうちく-」や、すこし細長いかたちをした「淡竹-はちく-」。
それらの竹を高圧釜や、炭作りでつかう炭窯-すみがま-に入れて燻-いぶ-すことで、ほかにはない竹のコクのある風合いがうまれます。
この特別な素材を、弊店では「炭竹-すみたけ-」と名付けて呼んでいます。

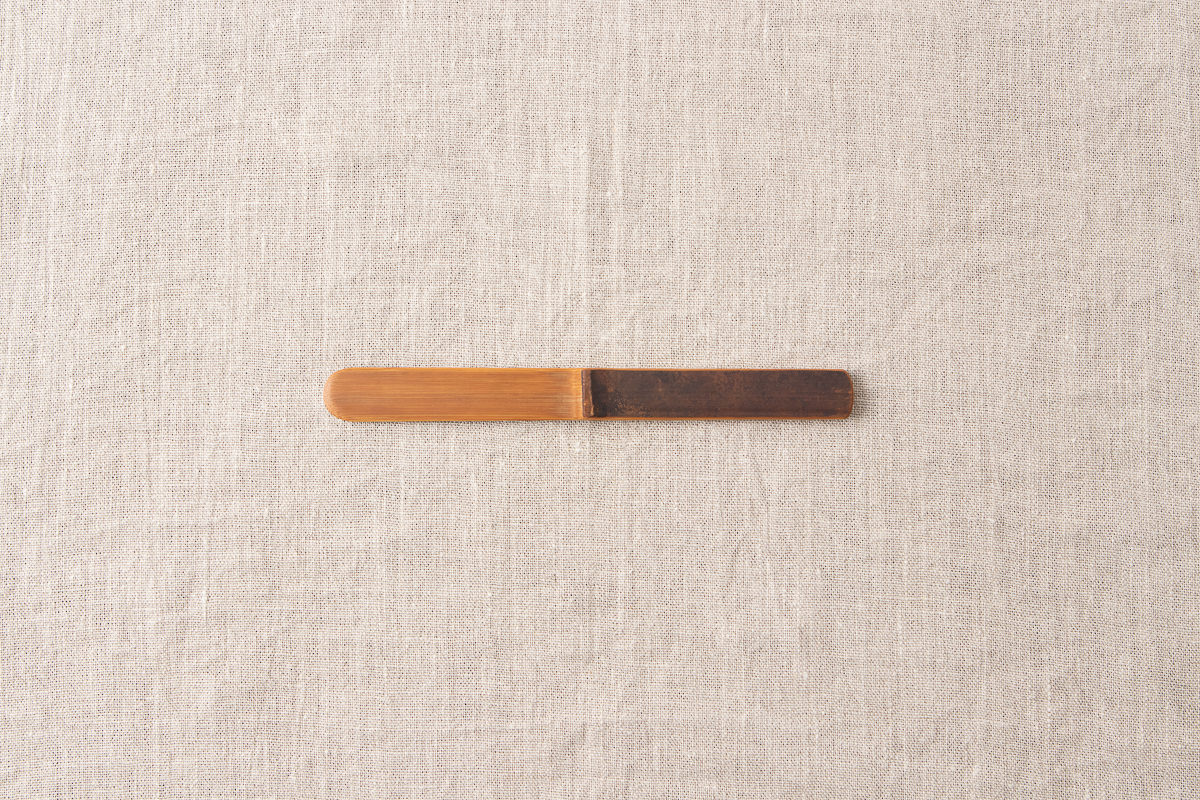
こちらは「万能へら」。アイスキャンディのスティックのようなかたちをしていますが、しっかりとした太さと厚みがあります。 
こちらがへらの先で、塗ったり練ったり和えたりするところです。 
へらの刃先は、1mmもないほどの薄さ。とはいえ、シュッと指を傷つけてしまうような鋭さはなく、やさしい手あたりです。 
へらの先端もなめらかな丸みを持っています。食材を和えたりするときにも、器や鍋を傷つけにくい仕様です。 
ヘラの柄は握りやすいように厚みがしっかりと取られています。炭竹ならではの燻した竹の表情にも味わいあります。 
その名前のとおり、いろいろな場面でお使いいただけます。サラダを和えたり。 
ジャムや餡を塗ったり。ケーキのクリームを塗るとき、餡を練るときにも。 

ほかにも、おひたしを和えたりや納豆をまぜたりと、お料理のいろいろな場面で活躍します。 

こちらはバターナイフです。万能へらにくらべるとシャープなデザインです。 
ナイフの刃部分です。写真の刃上側は平らに、下側はバターが切りやすいようナイフ状になっています。 
こちらも薄いつくりですが、シュッと指を傷つけてしまうような鋭さはありません。やさしい手当たりです。 
ナイフの柄は握りやすい厚みになっています。燻された竹の風合いが感じられます。 
裏面の様子です。 

刃のところでバターを切り、平らに塗り広げたいときは、上の部分の平らなところを使います。 
左利きの方もおなじような使い方ができます。

いい道具を使って料理をしたり食事をしたりしていると、
なんだかとてもいい時間を過ごしているような気分になります。
そんな日々の小さな幸せを作り出してくれそうな、2つの道具です。
どちらかお好みのタイプをお選びください。

__下本一歩さんの竹カトラリー__
高知の山あいに工房を構える下本一歩-かずほ-さんは、
もともと、土と石だけで築き上げる炭窯を地域の方々とともに作り、
その炭窯をつかってカシやナラの木を炭にする
「炭焼き」を本業とされていました。
炭を焼く工程で出る大量の煙に、ご自身が削った竹のスプーンなどを
つるして直に当てることで出来上がったものをきっかけに
炭窯で燻-いぶ-した竹のカトラリー作りを本格的に始められました。
日本の各地で、今では地域によっては邪魔者とまで言われている竹。
下本さんは自ら山に入って切り出し、熱処理を施したあとに
自作の炭窯で燻し、真っ黒に色付いた竹をつかって
生活の道具としてのカトラリーを作られています。
下本さんの作られるものは、シャープな印象ながら、
どこか穏やかな厚みや丸みも感じられ、見た目だけではなく
手に触れるとやさしく、もちろん実用的という奥深い魅力を持っています。
長くつかうほどに竹の風合いはやわらかくなじんで、
もともと持つ「シャープで、穏やか」な印象はそのままに
より愛着が深まり、日々の食卓に、つかう人の気分に、
小さな彩りを加えてくれるのではないかと思います。





